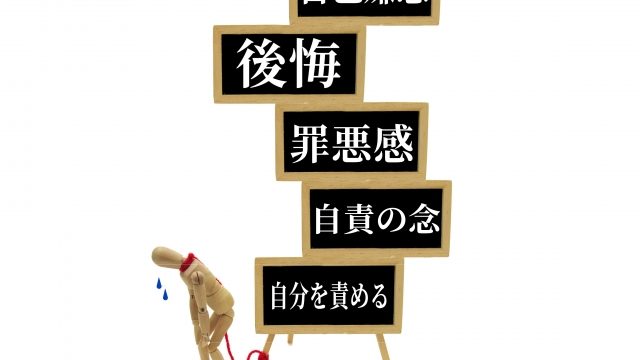一生懸命に文を書いたのに伝わらない
どうしたら文章力が上がるのかがわからない
こんな人に向けて、1日5分で文章への苦手意識がなくなる勉強方法、簡単にできる「伝わる文章」の作り方を紹介していきます。
目次
多くの聴覚障がい者が文章苦手な理由
苦手な理由がわかれば、対策もできます。だから、まず苦手な理由を分析していきましょう。
聴覚障がい者の私の経験をもとに分析していきますので、ご参考していただけると嬉しいです。苦手な理由のあとに、対策方法を書いていますので、こちらも参考してみましょう!
聞こえる人は自然と情報が耳に入ります。逆に聴覚障がい者は目からの情報でしかないので、圧倒的な情報量の差があります。その分、手と足を使って、自ら情報を集めないといけません。
また、手話は助詞を省いて表現する場合が多い。
例えば、初めて会うとき、必ずといってもいいほど自己紹介します。そのとき、聴者の場合は
という風に言うのではないでしょうか。
手話の場合は、
「僕」「名前」「太郎」「です」という風に単語ごとで表現します。つまり、助詞を省いている場合が多い。
実際に聴覚障がい者の私が以下の対策方法でやって、文章力が向上したと実感しています。
- 読書するなどで活字を触れる機会を増やす
- 聴者とコミュニケーションの機会を増やす
- ブログやX(元Twitter)などのSNSで発信
- 文章のプロから学ぶ
文章力を向上させる2つのステップ
聴覚障がい者の多くが文章が苦手な理由を理解していただけたと思います。理由がわかると対策もできます。
- 健聴者と聴覚障がい者の情報量の差
- 手話では助詞を省いての表現が多め
聴覚障がい者の私が実際にやった勉強方法を紹介していきます。
ステップどおりに踏んでいけば、ほとんどの人は上達できます。
STEP1 プロの文章を丸写し
STEP2 実践を重ねる
STEP1 プロの文章を丸写し
その前に一つ大事なことをお話します。何も考えずに丸写ししても上達はしません。
丸写ししながら、なぜこんな書き方をするのかを考えながらやることです。
例えば、
台風が来たので、学校を休みました。
という文があります。これを写すとき、「学校を休んだ理由を書いているんだな」と感じながら写すのです。
このようにいろいろと感じながら写していくと、文章作成していくうちに、この「表現はおかしい」「言葉を変えたほうがいい」など、いろいろと気づけるようになってきます。
めんどうくさい作業かもしれません。しかし、この作業を徹底的にやっていくと文章力の爆伸びができます。
聴覚障がい者の私が実際に丸写ししたときに使った書籍を紹介します。
伝わる!文章力が身につく本
ステップ式できちんと踏んでいけばレベルアップできる内容
項目ごとの例文とその改善例があり、どこをどう直せばいいかを具体的に書いてくれている
伝わる!文章力が豊かになる本
ひとつ前に紹介した「文章力が身につく本」の更なるレベルアップしたい方におすすめ!
豊かな表現力も身につくので、面白いように文章を操れるようになれる!
一瞬で伝わる神ワザ!文章力大全
文章作成の基本をもっと身につけたい方におすすめ!
辞典のようなもので、どう書いたらいいか悩んだときに役に立つ1冊
STEP2 実践を重ねる
本の内容を1日2ページ丸写していくと、プロ並の文章力が身につきます。それと同時にLINEや筆談などで何度も文章を書いていくとみるみる上達していきます。
例えば、LINEでのやりとりするとき、学んだ文章の書き方を意識していくと上達でき、読む相手もスーッと理解できるようになります。
双方にとってメリットがあるので、ぜひやってみてほしいです!
実践するとき、意識してほしいのが、「読む相手」です。つまり、読む相手がわかるように書くことです。
伝わる文章の型の「PREP法」
文章の本を読んだ方は一度は見たことがある「PREP法」があります。
PREP法とは、伝わる文章の型で、当てはめていけば、筋が通っている限り、ほとんどの場合、伝わります。結論で始めり、結論で終わるという型とも言えます。
- P・・・Point(結論)
- R・・・Reason(理由)
- E・・・Example(具体例)
- P・・・Point(結論)
よく見ると、サンドイッチのように、結論と結論との間に、Reason(理由)、Example(具体例)を挟んでいます。
伝わる文章の型の「PREP法」は、プレゼンなどの会話にも役に立ちます。長い話を聞くと、多くの人は最初の話を忘れます。例えば、30分以上の講演で聞くとき、最初の話を忘れる人が多いです。だから、「書く」だけではなく、プレゼンなどの会話にも役に立ちます。
お気づきの方もいるかもしれませんが、上の文章も、「PREP法」で作っています。
- 伝わる文章の型の「PREP法」は、プレゼンなどの会話にも役に立ちます。(結論)
- 長い話を聞くと、多くの人は最初の話を忘れます。(理由)
- 例えば、30分以上の講演で聞くとき、最初の話を忘れる人が多いです。(具体例)
- だから、「書く」だけではなく、プレゼンなどの会話にも役に立ちます。(結論)
このように、「PREP法」を当てはめていくと、自然と伝わる文章になります。
さらに自然と短い文を作れて、しかも、伝わる文章になります。
慣れるまでに時間がかかりますが、身につくと間違いなく仕事の効率が上がります。
【補足】具体例の説明が苦手な方は「例えば」から書いていくのがおすすめです。
書く練習をやらず、文章力は上達できるの?
ここまで、文章力の上達方法のひとつとして「書いていく」方法を紹介しました。
とはいえ、「書いていくのがめんどう」という方がおられるかもしれません。
書く練習をやらず、文章力上達はできますか?
これはよくある質問です。聴覚障がい者の私の個人の考えですが、
「読書だけでは上達しません。しかし、上達するためには読書も必要」
読書は「語彙を増やす」「豊かな表現力が身につく」ための手段だと考えています。
簡単に一言を表すと、著者の書き方を学べるのです。
聴覚障がい者の私は池井戸作の小説が好きです。絶体絶命のような状況からの逆転劇のような内容が多く、めくる手が止まらないほどの面白さが好きです。
さらに、池井戸さんの文章の書き方も魅力を感じており、テクニックを学ばせてもらっています。
ついでに池井戸作の小説を読んでみたくなった方におすすめしたい2冊があります。
民王
<div class=”simple-box2″><p>国家的な危機に直面している中で、突然、内閣総理大臣の父と就職活動中の息子が入れ替わります。つまり、親子の入れ替わりで、息子が突然、総理大臣になってしまった。しかも、父親の体!逆に父親は就職活動中の身になってしまった。しかも、息子の体!
親子の入れ替わりでそれぞれの問題を解決していくお話になっています。</p></div>
空を飛ぶタイヤ上・下
<div class=”simple-box2″><p>1人の男性が不正を隠している大手企業に挑む物語。一人の男性は赤松運送の社長で、部下が運転したトラックのタイヤが突然外れ、通行人の女性に直撃してしまった。タイヤが外れたのは、整備不良であれば、赤松運送の責任になるが、警察などの方々で実際に確認したところ、部下の整備士はきちんと仕事をこなしていた。では、タイヤが外れたのか?
その真相を暴くすべく、赤松運送の社長が立ち向かう物語になっています。</p></div>
SNSで発信
ブログやX(元Twitter)などで発信すると、文章力が磨けます。
ブログやX(元Twitter)は無料で始められます。
無料でブログ開設したい方は、はてなブログがおすすめ。
X(元Twitter)で発信したい方は、アカウント作成はこちら
PREP法を使いこなせるようになりたい方は、X(元Twitter)がおすすめ。140文字制限になっているので、長い文を140文字以内に収まらないといけません。例えば、今聴覚障がい者の読者のあなたが読んでいるこの記事を140文字以内にPREP法でまとめられます。このように、TwitterでPREP法の練習ができます。
長い文章を書くのが好きな方はブログがおすすめです。文字数を気にせずにたくさん書けます。そのとき、PREP法を意識して書いていくと、文章力がかなり上達します。
さらに「好きなこと」を発信していくと、今後、内容次第で収益化が可能になってきます。
もし、ビジネスをやるなら、売れるためには文章力が必須になってきます。
まとめ
多くの聴覚障がい者が文章を苦手とする主な理由は「聴者との情報量の差」「助詞を省いての手話で会話」でした。
苦手克服方法のひとつとして、プロの文章をひたすら丸写しすることです。とはいえ、何も考えずに丸写しするのではなく、なぜこの書き方をするのかを考えながら写していきます。
さらに読書もしていくと、著者の書き方にも参考になれて、豊かな表現力が身につくので、更なる文章力の上達の期待ができます。
大事なのは、読書するだけで、文章力は上達しません。ただ、先ほど供述したように、「読書だけでは上達しません。しかし、上達するためには読書も必要」ということを頭に入れてほしいと思っています。
プロの文章を「なぜこの書き方なのか」と考えながら実践を繰り返していくと、みるみる上達してきます。さらに読書もしていくと、さらに上達できます。
1分10分でもいいので、ぜひやってみてほしいです。
また、「文章の書き方ががわからない」「勉強の仕方がわからない」といった悩みをお持ちの方、または添削してほしい方はお問合せより、ご相談していただけると対応します。

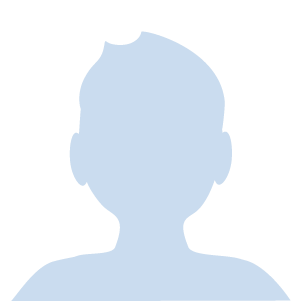
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37cdaabf.a25124a8.37cdaac0.59ea6738/?me_id=1262790&item_id=10573451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru-ds%2Fcabinet%2Fb%2F1%2F160%2F9784471191160.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37cdb29c.991feada.37cdb29d.105a07b3/?me_id=1220950&item_id=13400669&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_597%2Fneobk-1066371.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a21e47f.681e35bb.1a21e480.f33eaae7/?me_id=1213310&item_id=20248355&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3472%2F9784413113472.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15835e60.d5244341.15835e61.3f151e6b/?me_id=1278256&item_id=18636434&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7508%2F2000007817508.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fb95b89.3235e31d.1fb95b8a.e487fd3f/?me_id=1378792&item_id=10403344&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frenet20%2Fcabinet%2Fitem_photo%2F001096%2F0%2F0010960532.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)