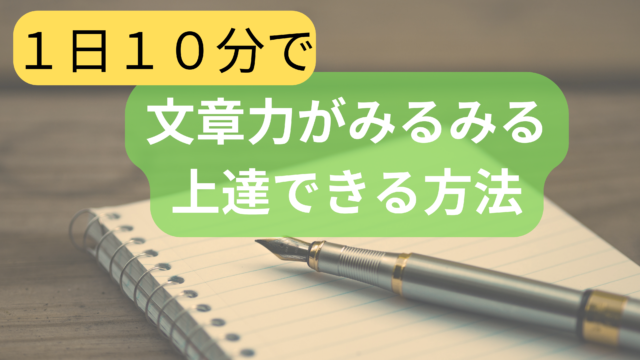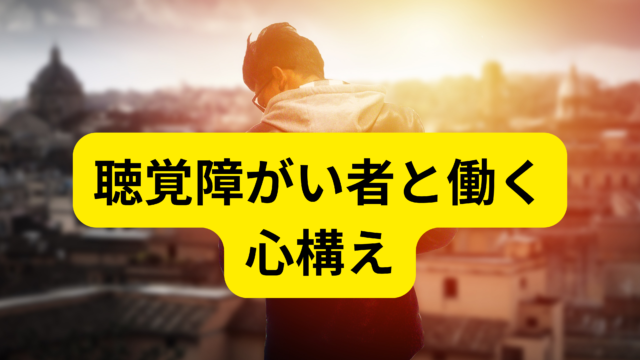「聴覚障がい者ともっとスムーズに話したい」と思ったことはありませんか?
- どう話しかければいいかわからない
- 伝えようとするけど、うまくいかない
- 聴覚障がい者の特性 を知ると、”伝え方” がわかる
- 避けるべきNG対応 を知れば、誤解を防げる
- 筆談やジェスチャーのコツ を学べば、スムーズに話せる!
この記事では、 「よくある間違い」「すぐにできるサポート」「聴覚障がい者が嬉しいと感じた対応」 を 具体例付きで紹介!
この記事を読んでできること
- 聴覚障がい者との会話で困らなくなる
- 誰でも簡単にできるサポート方法がわかる
- 「ありがとう!」と言われる関係性を築ける!
目次
聴覚障がい者への理解を深めるメリット
こんな壁がありませんか?
- どう接していいかわからない
- 話しかけるのをためらってしまう
そんな‟壁”をなくすためには、まず「知る」ことから!
知ることで得られる3つのメリット
- 関係がスムーズに→相手の特性がわかれば自然な対応ができる
- 相手の立場に立って考えられる→誤解や気まずさを減らせる
- 感謝される経験が増える→「ありがとう!」の言葉で嬉しさと充実感が得られる
本当にあった聴覚障がい者の対応エピソード
よくある‟間違った対応”
- 名前を呼ぶだけで気づいてもらえると思っている(みんな気づくとは限らない)
- ゆっくり大きな声で話せば伝わると思っている(ゆっくり話しても通じない人もいる)
- 手を肩に強く叩いて注意を引こうとする(驚かせてしまう)
より良い対応の方法
- 筆談やジェスチャーを活用する
- 相手の注意を引くときは軽く肩を叩いたり、手を振る
- 顔を見てゆっくり大きく話し、必要なら文字で補助する
実際の体験談:聴覚障がい者の私も、社会人のなりたて頃、健聴者の職場環境に戸惑いました。
例えば、呼ばれたのに気づかないとき、無視されたと誤解を与えたり、ゆっくり大きく話して伝わったと思い込まれたり、色々とありました。
しかし、今では周囲が「筆談ボートで書いてくれたり、肩を叩いてくれたり」などの工夫をしてくれるようになり、コミュニケーションがスムーズになっていきました。
聴覚障がい者と聴者のマナーの認識の違い
これは聴覚障がい者と健聴者のマナーの認識の違いの動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=YJ4ZFhLv37gより引用
聴覚障がい者の私の体験談:17年間、ろう学校で健聴者との関りが少ないまま、育ってきました。
その結果、社会の世界に入ったとき、マナーの認識の違いで苦労しました。例えば、ろう者の世界では当たり前だった「手招き」で、社会の世界で使うと、注意されました。
今では、仕事するときは、健聴者のマナーで、ろう者の世界ではいつも通りに接しています。
聴覚障がい者の特性
代表的な聴覚障がいのタイプ
- 片耳のみ聞こえる
- 大きな音だけ聞こえる
- 補聴器や人工内耳を使用している
コミュニケーション手段
- 手話→ろう者の第一言語
- 筆談→手話ができなくても、紙やスマホなどで伝えられる
- 口話(読唇術)→全員できるわけではないことを理解する
- 音声認識アプリの活用→人の声をスマホの画面上に文字として表示される
音声認識アプリのUDトーク
聴覚障がい者の私の職場で、朝礼などで使っている音声認識(音声翻訳)アプリです。
人の声をスマホ画面上に文字として表示されるので、円滑にコミュニケーションが可能です!
聴覚障がい者と筆談するときの注意点
筆談と言えば、普通に書いて、お話すればいいと思うかもしれません。しかし、実はそんな注意点があります。
まず、注意点のひとつとしては「難しい言葉」を使わないことです。
筆談の注意点を詳しく知りたい方はこちらの記事→(【健聴者必見】聴覚障がい者と筆談する際の3つの注意点とは? | ユーケン。チャンネル)
手話の勉強を始めたいとき
手話の勉強を始めるなら、まず、聴覚障がい者と手話で会話することから!
本で勉強するのもいいのですが、実際に手話を使って会話したほうが上達が早いです。
本や動画などで調べるのは補助的として使っていただけたらと思っています!
手話単語を調べられるサイトはこちら→NHK 手話CG 単語検索サイト
指文字を覚えたい方はこちら→手話の指文字表(50音)【相手から見た形】イラスト付き・由来で覚える 無料ダウンロード・印刷|幼児教材・知育プリント|ちびむすドリル【幼児の学習素材館】
聴覚障がい者と関わるうえで避けるべき対応
例えば、こんなことやっていませんか?
- 後ろから話しかけられる→気づかないまま無視していると思われる
- マスクをつけたまま話す→口の動きが見えないため、より伝わりにくい
- 大声で話せば伝わると思っている→音量より視覚情報のほうが大事(文字など)
どうすればいい?
- 相手の正面に立ち、軽く手を振るもしくは肩を叩く
- どうしてもマスクを外したくない場合、筆談やスマホを活用
- 表情やジェスチャーを意識して話す
聴覚障がい者の私の体験談:コロナ禍で一番だったのがコミュニケーションでした。職場では理解してくれて、すべて筆談で対応してくれるようになりました。
とある店で、弁当を買うとき、マスクをつけたレジの店員が「レジ袋どうしますか」と言われていると思い、手で「×」の形を作り、「いらない」と伝えました。すると、次に何か言われてきました。とりあえず、「×」の形を作って身振りで示しました。
そしたら、バーコードを読み終えた弁当をそのまま清算用カゴに入れていくところを見て、身振りで慌てて箸をくださいと伝えました。
さっきいらないって言ったんじゃない?と少し不思議そうな顔しました。
この体験談のように、マスクをつけるとより伝わりにくくなります。だから、聴覚障がい者と会話するとき、マスクを下げてゆっくり大きく話すことです。
コロナやインフルエンザなどでマスクを下げたくない方は、筆談などで会話する方法もあります。
聴覚障害者(ろう者)に関する書籍の紹介(僕のおすすめする本)
この本は聴者とろう者の認識のズレ、言葉のズレなどをまとめた1冊です。
この本から一部紹介させていただきます。
「つもり」という言葉に対して、聴覚障害者は「実際にやらなかった方が多い」とされていますが、聴者は「実際にやった人が多い」とされています。
聴覚障害者の私もこの本から「つもり」について、新しい気づきを得て、これから極力「つもり」という表現を使わないようにしています。
このように、ろう者も聴者も新しい発見、新しい気づきが多く得られる本です。
まとめ
聴覚障がい者との関わり方を知るだけで、コミュニケーションの壁がなくなる!
まずは「正しい理解」からスタートしよう!
手話に興味があるなら? 「手話を覚えたいけど、どう勉強すればいいかわからない…」
→手話の勉強法詳しく知りたい方はこちらのページへ!→(手話の勉強方法 -初心者にもおすすめの勉強方法を詳しく解説- | コラム | SureTalk)
ユーケン。チャンネルの運営者に聴覚障がい者のことを知りたいなら公式LINEへGO!![]()
公式LINEに登録したら、聴覚障がい者のことで聞きたい内容をメッセージを送ってみてください。運営者が24時間以内に返信します。