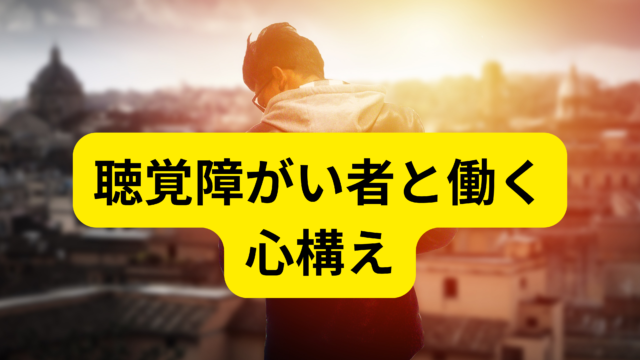聴覚障がい者のために何か力になりたい方へ
- 職場で聴覚障がい者の人が入ってきたけど、どう接したらいいのかわからない
- 聴覚障がい者をサポートしてあげたいけど、何を始めたらいいかわからない
と悩んでいる健聴者に向けて、聴覚障がい者の主な特性を知ると、どんなサポートしたらいいかがわかるようになってきます。
この記事では、聴覚障がい者の特性をはじめに、困っていること、その対策方法を紹介します。聴覚障がい者へのサポートを通じて、「聴覚障がい者の方の生活や社会との接点が広がることが嬉しい」という声もありました。
まず、聴覚障がい者の主な特性を知ってもらって、困っていること、その対策方法を紹介していくので、ご参考していただけると嬉しいです!
目次
聴覚障がい者の特性
まず、聴覚障がい者の主な特性を簡潔にまとめてみました。
- 聞こえの程度は人によってさまざま、口話レベルもさまざま
- 聴覚障がい者の多くの第一言語が手話
- 聴者とのコミュニケーション方法が主に筆談
特性を簡潔にまとめると以上の3つです。
多くの健聴者が持つ「聴覚障がい者」へのイメージは「耳が聞こえない」とされています。
「聴覚障がい者」=「耳が聞こえない」というイメージは間違いではありません。ただ、少し細かく言うと、少し聞こえる人もいます。または、片耳しか聞こえない人もいます。
- 軽度難聴(少し聞こえる)
- 中度難聴(普段の会話が聞こえない)
- 重度難聴(大きな声でも聞こえにくい)
- ろう(全く聞こえない)
聴覚障がい者の私は「ろう」です。
聴覚障がいとコミュニケーション
聴覚障がい者の主なコミュニケーションに関することが以下のとおり
- 聴覚障がい者の第一言語が手話→聴覚障がい者の多くは手話で会話
- 面に向かって口を大きくゆっくり話す→これができれば、少しでも伝わるようになる
- 聞こえのレベルに関係なく普通に話せる人もいる→補聴器をつけたら普通に話せる人もいる
- 聞こえの程度は人によって様々で対応方法も多少変わる。
- 聴覚障がい者の多くの第一言語が手話
- 面に向かってゆっくり大きく話してくれたら理解できるろう者も多くいる。
コミュニケーションの重要性
まず、以下の画像を見て何か感じましたか?

聴覚障がい者を悩ませているコロナ禍 | みんなの障がい | 全国の障害者・福祉福祉施設が見つかるポータルサイト (minnanosyougai.com)より引用
緑服を着た男性が聴覚障がい者、赤い服を着た女性が健聴者です。
健聴者の女性は聴覚障がい者の方に何かを伝えようとしています。しかし、健聴者の女性はマスクをしているため、伝わりにくい様子を描かれています。
マスクで口の形が全く見えないため、内容全くわかりません。だから、聴覚障がい者に何かを伝えたいときは話すときはマスクを下げることです。もしくは筆談をする。
また、後ほど詳しく供述しますが、マスクを下げるのに抵抗がある方は透明マスクを検討してみるのもおすすめです!
手話とマスク
手話初心者の方に「マスクしても、手話で表現したら内容わかるのでは?」と聞かれたことがあります。
確かにマスクで口の形が見えなくても手話で表現したら通じると思いますよね!
結論からお伝えすると完全に伝わるとは限りません。
以下の画像を見ていただくとわかるように、手話表現自体は同じです。しかし、顔を見ると表情が違うのがわかりますか?

手話通訳 マスク「口形の言葉」見えず/聴覚障害者が不安 (jcp.or.jp)より引用
聴覚障がい者の私も普段手話でやりとりしていますが、そこでマスクを着けて手話表現されると、手話自体はわかりますが、表情が見えにくいため、わかりにくいときがあります。
確かに文脈でイメージはできますが、表情と口の形を見えるようにするのが確実です。
それでもマスクしたい
先ほど供述しましたが、中には、コロナやインフルエンザなどの不安で、マスクを下げるのに抵抗する方もいます。
その方におすすめしたいのが、透明マスクです。
透明マスクしている健聴者に使ってみてどんな感じなのかを聞いてみました。ご参考していただけると嬉しいです。
透明マスクを使ってみての感想
- マスクと同じように使いやすい
- 息で透明の部分が曇るので、口の形が見えにくいと言われたことがあった。
息で透明の部分が曇るというデメリットもあるらしいです!
ぜひご参考ください!
聴覚障がい者に対してのよくある認識
これは、聴覚障がい者へのサポートに興味を持っている人、これから手話を始める人から聴覚障がい者の私によく聞かれたことを厳選してまとめています。
聴覚障がい者へのよくある認識
- 聴覚障がい者は口話できない?→聞こえなくても補聴器付けたら口話できる人もいます。
- 手話は聴覚障がい者同士でやるもの→健聴者との会話でも使います。例えば、最近テレビで見るようになった手話通訳なども含みます。
- 聴覚障がい者は文章苦手な人が多い→多いですが、最近、ろう学校で読書する時間などを設けているところがあり、これから苦手な人が減るのではと感じています。
また、聴覚障がい者について知りたいことがあれば、記事下のお問合せよりご連絡お願いします!
例えば、「聴覚障がい児は言葉を覚えるときってどうやる感じ?」「聴覚障がい者が仕事やるときって毎回筆談?」などでも気になることでも構いません。お気軽に質問を受け付けています。
聴覚障害者が困ること
仕事で困ること
主に聴覚障害者の私が仕事で感じた、困ったことを供述しています。ご参考していただけたら幸いです。
- 朝礼・夕礼などの内容がわからない。
- 忙しいからなのか、早口で指示されるが、内容把握しづらい。
- 放送の音に反応はできるが、内容は把握できない。
- スクリーンなどを使って説明される場合もあるが、簡単な内容にしか書かれてない。
- チャイムの音は聞こえるが、雑音の中では聞こえづらい。
- 上司に報連相する際、紙に書いて渡すが、書くのが面倒だからなのか無回答が多い。あるいは何の連絡もせず、進められたこともある。
- みんなは知ってて、自分は知らなかったことが多い。(聴覚障害者の仲間を含む自分には連絡なかった)
気づいた方も多いと思いますが、困っている部分のほとんどがコミュニケーションです。
チームで仕事するときはコミュケーションが重要です。しかし、コミュケーションができずに困ってしまうことはよくあります。
その中で一番困るのが「みんなは知ってて、自分は知らなかったことが多い。(自分には連絡なかった)」の部分です。
みんなは知ってて、自分は知らなかったという経験をお話します。色々ありますが、1つの事例を紹介します。
食堂の利用方法の変更
2020年コロナ流行時、食堂の利用方法が変わったという説明があった。そのお話があったのは、月に1回課全体で集まって課長による昼礼のときだった。課にいる聴覚障がい者は私を含めて4人。昼礼の基本的な内容は今月生産の状況、先月の品質の状況の報告だったが、その時は食堂の利用方法変更の説明があったらしいが、私たち4人は聞こえないためにわからなかった。
食堂を利用する聴覚障がい者は私を含め、2人。いつも通りに食堂を利用すると、食堂にいるスタッフの方に注意されました。「いつも通りに利用しただけなのに、なんで注意されるの?」と思いましたが、筆談をお願いすると、「コロナの影響で利用方法が変わった」と説明され、その方法に従いました。
職場仲間に確認すると、課全体の夕礼で食堂の利用変更の説明があったと知りました。課長による説明の時は、今月の生産状況、先月の品質の状況はスクリーンもあるので、「今月は忙しいな」「先月は品質不良が多かった」など理解できますが、食堂利用方法が変わったというのはスクリーンに映ってなかった。
仕事でのコミュニケーションの対策
私たち聴覚障がい者が仕事するとき、一番困っているのが
コミュケーション
だと理解していただけたと思います。
現在もやっているコミュケーション対策を紹介します。
もし、他にいい方法があれば、教えてください。
- 健聴者に手話を教える
- 音声翻訳アプリを使用
- 掲示板に足を運ぶ
ここに本文を入力
一つひとつお話していきます。
健聴者に手話を教える
簡単な手話でもいいので、少しずつ教えてきました。すると、手話を覚えたいと言ってくれて、今は勉強してくれています。感謝しています。
音声翻訳アプリを使用
音声翻訳アプリはUDトークです。
先ほどお話したように、食堂利用方法の変更のお話、聴覚障がい者の私たちに伝わってこなかった。その経験もあり、音声翻訳アプリをダウンロードし、連絡漏れがないように、班での朝礼や課全体昼礼のときは使っています。
また聞こえる人との会話するとき、役に立ちます。
掲示板に足を運ぶ
各職場に掲示板があります。貼ってくれる内容は「各職場の目標」「課長の方針」「生産の状況」「所長の方針」などです。
足を運んで、情報を掴んで、その方針に対して自分は何をしたらいいかを考えて行動しています。
聴覚障がい者が仕事でのコミュニケーションで困っている内容などを知りたい方はこの記事でも解説していますので、興味があればこちら→(聴覚障がい者の職場コミュニケーション問題を解決!実践できる方法とは? | ユーケン。チャンネル)
日常生活で困ること
仕事でコミュニケーションで困ることがほとんどだと理解していただけたと思います。先ほど仕事で困ることはコミュニケーションでした。日常生活で困ることは音です。
- インターホンが聞こえない。
- 電話しかお問合せできないところがあると困る。
先ほどの仕事で困ることの多くはコミュニケーションでしたが、日常生活は音で困ることが多いです。
ただ、最近では、支援機器やアプリなどの登場によって、解決しつつあります。
日常生活での対策
インターホンが聞こえない
時間指定してない宅急便や急な来客が来ても気づかない場合が多いです。聴覚障がい者の私が一人暮らしを始めて8年ですが、特に急な来客来ても気づかない場合が多いです。
今では、モニター付インターホンがついてる物件、配線不要のインターホン取付しており、急な来客来ても気づきやすくしました。
このワイヤレスチャイムは音だけではなく、光るので、耳が聞こえない方でも気づけます。また、読者のあなたが聴覚障がい者のお子様を持つ方であれば、提案をさせてください。
2階建てで、2階で聴覚障がい者のお子様が勉強しているとき、「ご飯ができたよ」とわざわざ2階まで階段を上って声かける方が多いのではないでしょうか。聴覚障がい者の私も学生のころはそうでした。
毎日2階まで上がって呼びに行くのしんどいという方は、このワイヤレスチャイムを提案します。
机の上にワイヤレスチャイムを置くと光っていることに気づけます。
少し見にくくて申し訳ないですが、聴覚障がい者の私はパソコンの下にワイヤレスチャイムを設置しています。
家ではパソコンに向かって作業することが多いので、パソコンしていくうちに光ると急な来客でも気づけるわけです。
さらに配線不要なので、どこでも設置できます。だから、聴覚障がい者のお子様の机の上に設置し、お母さまが冷蔵庫などに呼び出しベルを設置するとキッチンにいながら、呼び出しが可能になります。
電話でしかお問合せしか出ないところあると困る
これは電話リレーサービスができるまでは、電話でしかできないところへのお問合せは、非常に困っていました。その時は親に頼んで電話をお願いしました。今では、電話リレーサービスのおかげで、電話できるようになりました。
電話リレーサービスとは以下の画像の通り、電話している人と電話を受ける人との間に手話オペレーターが立ち、通訳してくれるので、話ができます。

総務省|電話リレーサービス (soumu.go.jp)より引用
電話でしか受け付けてないところへ電話かけるとき、このサービスがあるので、非常に助かります。
手話を始めてみたい
この記事を読んでみて、手話を始めてみたいと思っていただけるととてもうれしいです!
すでに手話を始めている方は飛ばしてもらっても構いません。
手話はスポーツと似てると、聴覚障がい者の私個人的に感じています。なぜなら、身体で覚えるからです。スポーツは知識として頭に入れるより身体で覚えさせたほうが上達します。
手話はスポーツと似てて、実際に手話を使って、1000回以上の対話を重ねたほうが上達への近道です。
手話の学習方法を詳しく知りたい方はこちらの記事へ(【必見】実際に聴覚障がい者と会って手話で会話したほうが早く伸びます | ユーケン。チャンネル)
聴覚障がい者のことを理解するために
最後まで読んでいただきありがとうございます。聴覚障がい者が特に困ることはコミュニケーションです。
今では、手話普及はもちろん、それに支援機器やアプリなどなどの登場でコミュニケーションができるようになりつつあります。
ただ、まだまだコミュニケーションの壁はたくさんあります。先ほどの「仕事で困ること」でお話があったように、今でもまだまだあります。
理解してもらうために聴覚障がい者自分自身の努力もそうですが、健聴者の読者のあなたのご協力も必要です。
差別が少しずつ解消しつつあるのは、聴覚障がい者の方々だけではなく、健聴者の方々のご協力のおかげです。
聴覚障がい者の私も、活動のひとつとして、この記事を作成しています。健聴者の読者のあなたも理解していただいて、手話を始めるきっかけなどになっていただけたら非常にうれしいです!
ただ、コミュケーションするとき、1つの言葉に対する聴覚障がい者と健聴者の認識が違う場合が多いです。
例えば、私たちがよく使う「~つもり」があります。これは健聴者にとっては「やる」方向で言っているのではないでしょうか。聴覚障がい者の場合は「やらないかもしれない」という意味で言っています。
聴覚障がい者の私も注意されるまでは「~つもり」はやらないかもしれない意味で言ってしまいました。
それを勉強できる書籍がこの「ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ」です。
この本を読むと、言葉の認識のずれが学べるので、健聴者の読者のあなたが聴覚障害者に指導している先輩や上司であれば、ぜひ購入して、言葉のずれを理解していくと対応が変わるはずです。
まとめ
聴覚障がい者の困ることの多くはコミュニケーションです。まず、聴覚障がい者の特性を知ることから始めていきましょう。
復習として聴覚障がい者の特性は以下の通りです。
- 聞こえの程度は人によってさまざま、口話レベルもさまざま
- 聴覚障がい者の多くの第一言語が手話
- 聴者とのコミュニケーション方法が主に筆談
特性を簡潔にまとめると以上の3つです。
また、支援機器やアプリなどの登場でコミュニケーションの円滑化になりつつあります。しかし、まだまだ壁があります。
とはいえ、どんな対応をしてもコミュニケーションできないといった悩みをお持ちの方はお問合せよりご相談ください。
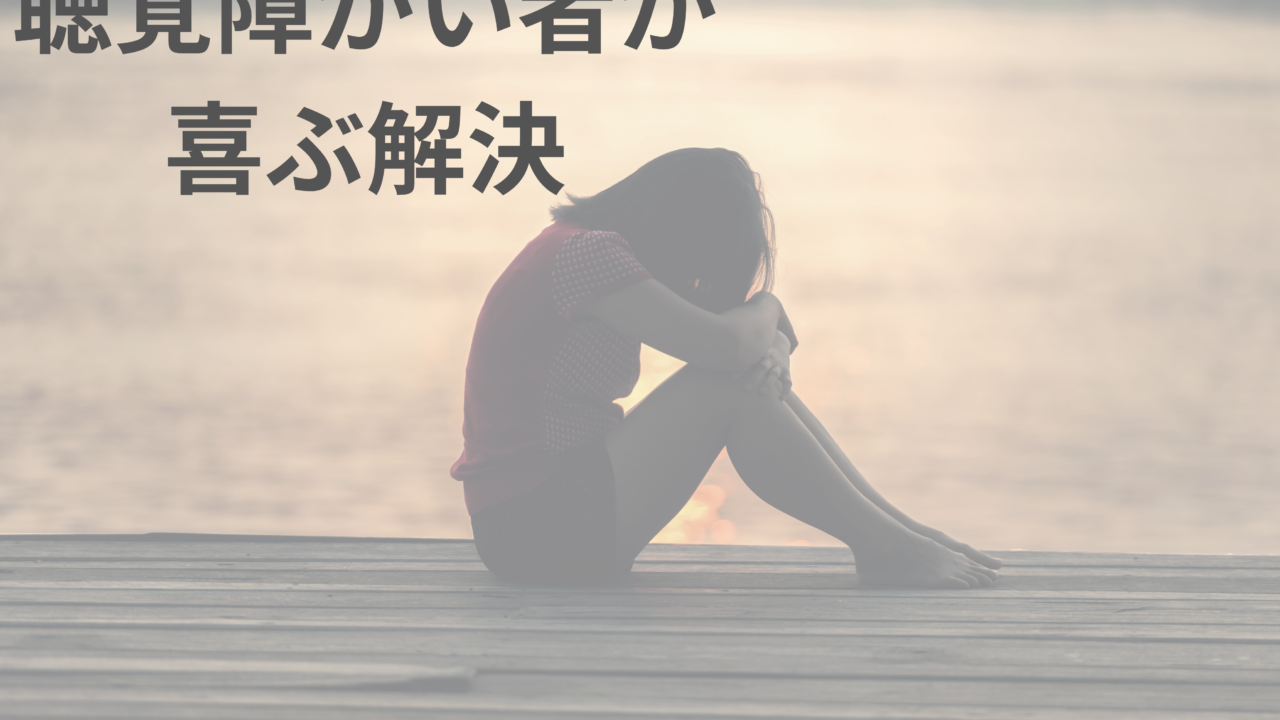
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4508acb7.2ce3d30e.4508acb8.744cb8e5/?me_id=1369892&item_id=10000511&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frelaxa-from2%2Fcabinet%2Fevent%2Fcoupon500%2Fclrwinmask.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e44f6bf.af17655b.3e44f6c0.5343c9a1/?me_id=1369817&item_id=10039196&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftispeed%2Fcabinet%2Fimg74%2F51h5svu242l.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a21e47f.681e35bb.1a21e480.f33eaae7/?me_id=1213310&item_id=13446103&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0084%2F9784863720084.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)