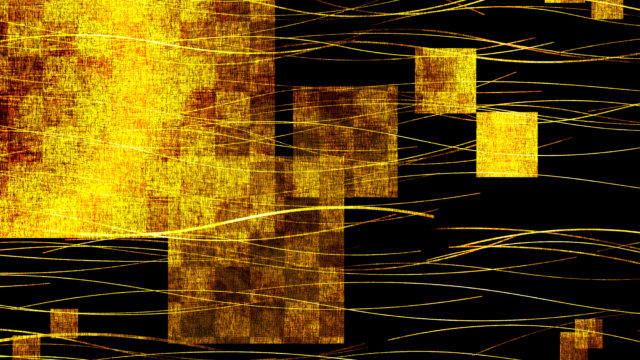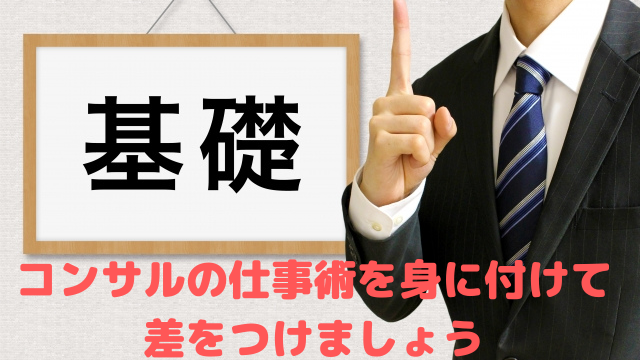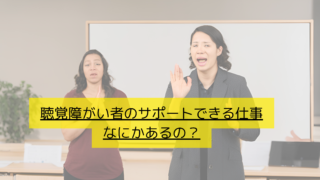【健聴者のあなたへ】 あなたはこんな経験ありませんか?
- 聴覚障がい者と筆談したけど、伝わらなかった
- 筆談しようとしたけど、どう書けばいいかわからなかった。
- 電子ボードを使ったけど、すぐに消してしまい困らせた
聴覚障がい者を相手に筆談する健聴者のよくある悩みですが、以上の3つのミスをしないための筆談のコツを紹介します。
はじめに:こんな経験ありませんか?
ある日、カフェで友人と話していたAさん。 隣の席には、聴覚障がいのある方が座っていました。
「すみません、ちょっといいですか?」
「……(筆談で会話したいみたい)」
そこでAさんは、スマホのメモアプリを開き、急いで文字を入力!
でも、いざ見せると…
「字が小さくて読めない!」
「文章が長すぎて何を伝えたいのかわからない!」
一生懸命書いたつもりだったのに、うまく伝わらない…
そんな経験はありませんか?
筆談は、聴覚障がい者とスムーズにコミュニケーションを取るための大切な手段ですが、ちょっとしたポイントを意識するだけで、驚くほど伝わりやすくなります!
本記事では、筆談をするときのコツやNG例・OK例を紹介していきます。
筆談のメリット
筆談は、手話がわからない人でも 確実に相手に伝えられる コミュニケーション手段です。
- 誤解なく、正確に伝えられる
- 言葉の壁を超えて、誰でも使える
- スマホやメモ帳があれば、すぐにできる
しかし、書き方を間違えると「かえって伝わりにくくなる」ことも!
そこで、筆談のポイントをチェックしていきましょう!
目次
なぜ必死に文字を書いても伝わらないのか
まず結論から書くと、難しい言葉を使うからです。
難しい言葉だと伝わりにくい原因は手話です。
聴覚障がい者が生きていくために最低でも手話が必要です。しかし、手話は文章どおりに表現するわけではない場合が多いです。
健聴者の場合、文章を書いているイメージで、文の流れの通りに話すのではないでしょうか。
口話の場合、文章通りに話すのに対し、手話の場合、セリフのない劇のようなイメージで表現します。
手話はセリフのない劇のようなイメージで、読み取るときも頭の中で字幕のないビデオを作るような感じをやっています。
だから、難しい言葉に慣れてないという聴覚障がい者も一定の方にいます。
筆談での失敗談(聴覚障がい者視点)
とある宅配便のお店へ行って、大きな荷物を届いてほしいとお願いしたところ、担当者が筆談してくれました。
でも、
- 「送れません」とだけで書かれていた。なぜ送れないのか知りたいのに。
詳しく知りたかったのですが、運が悪く、お客さんがたくさん並んでおり、聞けなかった。
そのあと、自分で調べたところ、ダンボールのサイズがオーバーが原因でした。そこでもう少し小さい段ボールを探して、荷造りして、もう一度お店へ行き、確認したところ、無事に発送できました。
失敗しないためのポイント
今回は聴覚障がい者の私が自分でなぜ送れないのかを調べましたが、宅配便は少なくとも荷物を送る仕事だと思うので、送れるように調整するのも一つの業務なのではないかと感じました。
だから、人の荷物を送るという自覚を持って、送れるように調整案などを書いてほしかったという気持ちもありました。
とはいえ、最近、後ほど紹介するUDトーク(音声翻訳アプリ)もあるので、これがあれば、忙しい状況でもスムーズにコミュニケーションできるようになります。
筆談がないとどうなるのか(聴覚障がい者視点)
聴覚障がい者にとっては、手話や文字が大事です。それがないと、コミュニケーションもできず、生きにくくなります。
あくまでも、聴覚障がい者の私の想像です。
もしも、突然、ある日、手話や文字が違法の世界になったら?
まず、音声言語のみになります。聴覚障がい者にとっては、情報を耳に入らなくなります。電話でしか受け付けないところもあるので、電話もできなくなり、宅配便などのやり取りも難しくなります。
仕事でのコミュニケーションも難しくなり、やめる聴覚障がい者が増えていきます。さらに、病気や行政への手続きが困っても、病院や役所への利用が難しくなり、身体がボロボロになったり、手続きを怠ったことで、罰金請求などが来ます。
車や家の購入も難しくなり、ホームレスだったり、仕方なく車を持たない生活を送ることになります。
聴覚障がい者の私の想像ですが、逆に言えば、文字や手話があるおかげで、私たち聴覚障がい者も生活できるのです。
だから、手話はもちろん、筆談も大事なのです。
聴覚障がい者に筆談するときの3つの注意点
難しい言葉をできるだけ使わない
先ほども供述しましたが、意識的に簡単な言葉で書くことです。
その分、文章が長くなりますが、伝わる可能性が90%へと上がります!
実際に、聴覚障がい者の私が、文章が苦手な聴覚障がい者の方に文章教育したことがあり、内容から一部抜粋したのが、以下の枠の内容です。
【普通の文章】
●医療ひっ迫している
【わかりやすく変えた文章】
●今、入院しないと命が危ない人がたくさんいます。でも、病院がいっぱいで入院できない人もたくさんいます。
【普通の文章】で伝えると、伝わりませんでした。そこで、【わかりやすく変えた文章】で伝えると、伝わりました。
少々、頭を使うかもしれませんが、意識的に簡単な言葉を使うと、その分、文章が長くなりますが、伝わる可能性が大幅上がります!
書かれた内容を汲み取るよう、心がける
始めて聴覚障がい者と接する健聴者によっては、最初はしんどいかもしれません。筆談の内容を正確に汲み取るのが大事になってきます。
そのためにまずは、文章の最初から最後まで注意深く読んであげると、汲み取りやすくなります。
汲み取る際の注意点が以下の3点です。
- 何度も読み返す→読み返すたびに少しずつ汲み取れるようになってきます。
- わからないときは確認する→確認せずに理解するとトラブルのもとに。
- 最初から最後まで読んであげる→汲み取りやすくなります。
聴覚障がい者の私の体験談:仕事で部品が足りないと気づき、上司に報告するために紙を書いて見せたところ、上司が「ん?どういう意味?」という顔をした。4回ほど読み直してくれて、「あぁ、部品が足りないということだよね?」と確認してくれました。
このお話のように、何度も最初から最後まで読んで、合っているかを確認するのが大事です。
わからないまま放置にしない
わからないまま放置にしない、3つの注意点の中で最重要です!
聴覚障がい者の私の体験談:仕事で、とあるとき、トラブルの報告のために紙を書いて見せたところ、少し怒った顔で、うなずき、そのまま去っていきました。
再度確認しなかった聴覚障がい者の私も悪かったですが、10分経ってもトラブルが解決してなかった。疑問を思い、もう一度、確認すると、やっと解決しました。
聴覚障がい者の私も、わからないのにわかったふりにされ、その後、トラブル発展につながったという経験があります。
おそらく相手は「忙しいし、とりあえず、内容はふわっと理解できたからええか」と思っただろう。
しかし、わからないときははっきりとわからないと伝える。理解できたが、もう少し説明がほしいときは「詳しく聞かせて」とやんわり伝える。
これが聴覚障がい者と筆談する際、重要な伝え方です。
【わからないときは】
●「わからない」もしくは「どういう意味ですか?」と伝える。
【理解できたが、もう少し説明がほしいとき】
●もう少し詳しく聞かせてくれる?とやんわり伝える。
筆談で逆にやってはいけないこと
- 小さすぎる字で書く(読みにくい!)
- 長すぎる文章を書く(読むのが大変!)
- すぐ消す(内容を確認する前に消される!)
聴覚障がい者の私の体験談:小さすぎて見づらく、しかも、長い文章。そして、すぐ紙を捨てられ、内容がわからなかった。そんなこともありました。
例えば、「明日の15時~ 4階会議室B 会議あります」
というシンプルな伝え方をすると、理解しやすくなります。
逆に筆談をうまくするコツを3つにとめました。
筆談するときの3つのポイント
1、文章を短く、わかりやすく!
NG例 「こちらの店舗の営業時間を教えていただけますか?」
OK例 「営業時間は?」
文章が長すぎると、読むのに時間がかかり、伝わりにくくなります。
「主語+述語」だけでシンプルに書く のがコツ!
2,文字は大きく、読みやすく!
NG例 (小さな字でギュッと書く)→「読みにくい。。。」
OK例 (大きな字でゆったり書く」→「これならすぐ読める!」
小さい字だと、見づらかったり、誤解を生んでしまうことも。
しっかり見やすい大きさで書くことが大切!
3,すぐ消さない!
NG例 スマホや電子ボードに書いた瞬間、すぐに消してしまう
OK例 相手が読み終わるまで、しっかりと見せておく
特に、電子ボードはワンタッチで消えてしまうので、相手が「OK!」と言うまで消さないようにしましょう!
筆談するとき、もう少し楽にしたい!
「筆談するとき、紙を使うから、コストが増えていく!!なんとかしたい!」
「できれば、仕事以外で紙を使わないでほしい」
働く健聴者のよくある悩み:筆談するための紙を使うと減っていくし、仕事で使う紙がなくなっていく。どうしよう。
聴覚障がい者の私の体験談:最初は紙を使って筆談していきましたが、あるとき、紙がなくなりました。
それで、筆談するための紙を取りに行ったり、探したりする手間が生じました。それで健聴者の方も「紙がない!取りに行かなきゃ!」と困らせてしまいました。
それで、紙がないとストレスで、「コミュニケーションが取れない」と思い、電子ボートを試してみたところ、紙を一切使う必要がなくなりました!
毎回、筆談で紙を使うとコストが増えていきますが、使わなくなってから増えなくなりました。
電子ボートがあると、コミュニケーションのストレスがなくなりました。
電子メモボード
「筆談のたびに、紙とペンを探すのは面倒じゃありませんか?」
電子メモボードなら
- ワンタッチで消せる から、何度でも使える!
- 軽量・コンパクト だから、外出先でも使いやすい!
電子ボードはボタン一つで書いた内容を消せる。繰り返し使えて、紙の無駄がない!
筆談をスムーズにしたい人はぜひ活用してみてください!
手のひらサイズの電子ボード
これは先ほど紹介した電子ボードより小さく、手のひらサイズです。
常にポケットに入れておくと、聴覚障がい者から急な報連相があっても、ポケットからパッと取り出せて、すぐ会話ができます。
大きめの電子ボードだと、ポケットに入らないので、取りに行くのがめんどうくさいのではないでしょうか?だから、ポケット版もおすすめです!
ただ、画面は小さいので、長文には不向きです。あえて、長文を書く場合、小さい文字で書くか、文章を削っていくしかありません。
例えば、「明日の15時~ 4階会議室B 会議あります」
という風に、シンプルにしても伝わります。
「電子ボード取りに行くのがめんどう」
常にポケットを入れて、聴覚障がい者の方に呼ばれてもパッと取り出せるようにしたい。
↓これがあれば、すぐ筆談可能に↓
UDトークアプリ
これはスマホアプリで、相手の声を文字化できるアプリです。要するに音声翻訳アプリです。
相手の声を順次に文字に反映してくれますが、発言内容の100%反映してくれるわけではありません。
簡単にいうと、声は合ってるけれども、反映内容は違うということです。
例えば、声は「おはようございます。今日も1日ケガなく頑張っていきましょう!」で言ってるけど、「ご飯ございます。今日も1日ケガなく頑張りましょう」という感じに反映されます。
ですが、多くの場合は前後の文脈の内容によって内容を掴める場合が多いです。それでもつかめなかった部分は直接確認します。これは先ほどの「わからないまま放置しない」と同じです。
実は、過去に使い始めたばかりのころ、UDトークに頼りすぎて失敗したお話があります。自戒の意味を込めてお話しますので、注意をお願いします。
UDトークに頼りすぎて失敗したお話
朝礼のとき、上司の発言をUDトークで文字変換してくれています。そのとき、「1時から社長の視察があるので、それまでに身の回りの整理整頓をお願いします」と書いていました。
聴覚障がい者の私は、1時だと思い込み、普通に仕事していました。すると、いきなり「なんで整理整頓しないの?」と職場仲間に言われました。
1時からだと思った聴覚障がい者の私は「社長の視察は1時からですよね?」と確認すると、11時からだったのです!
それで慌てて身の回りの整理整頓をして、視察開始ギリギリで済ませることができました。
その反省を活かして、視察などの大事なイベントがあるとき、UDトークに書いてる時間が合っているかを確認しています。
まとめ
聴覚障がい者と筆談する際の注意点は3つです。
- 難しい言葉を使わない
- 書かれた内容を汲み取るよう、心がける
- 分からないまま放置にしない
特に初めてのときは、書かれた内容を汲み取るのは難しいかもしれません。聴覚障がい者の私の経験上、コミュニケーションを何度も取れば、汲み取ってくれるようになりました。
始めの頃は、「意味が分からない」ということが何度も出てくると思います。わからないまま放置せず、わからないときははっきりとわからないと伝えてあげてほしいです。
また、聴覚障がい者向けの筆談の仕方を紹介している記事もあるので、興味があれば覗いていただけると嬉しいです!
記事はこちら→【聴覚障がい者必見】仕事で超役に立つ筆談でスーッと伝わる書き方とは | ユーケン。チャンネル
筆談に関する悩みがあれば、お問合せよりご相談ください。聴覚障がい者の私が回答させていただきます!
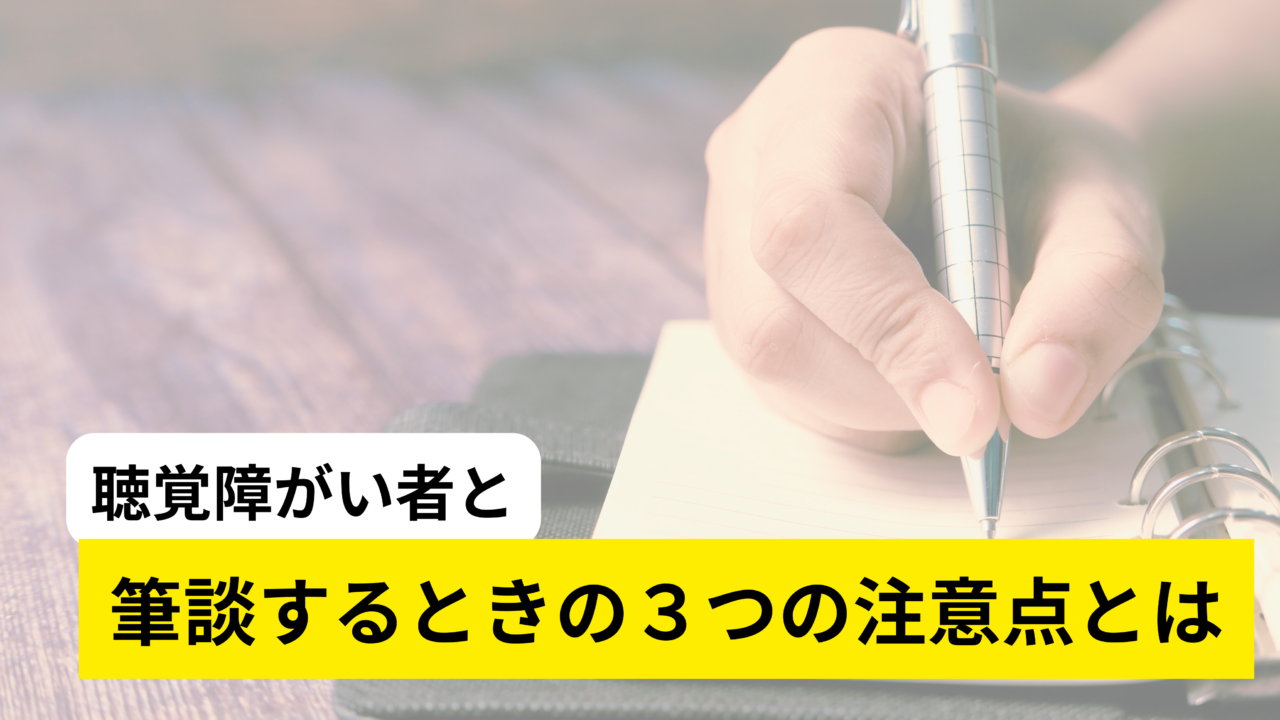
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/422fa8d3.b20e3ae4.422fa8d4.f7e4bd14/?me_id=1429099&item_id=10054542&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fokashashop%2Fcabinet%2F11137354%2F19819836_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/422fb994.59c2279d.422fb995.89e1c720/?me_id=1306087&item_id=10357203&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fmoccasin%2Fcabinet%2Fkyoyu192%2Fem02memo_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)